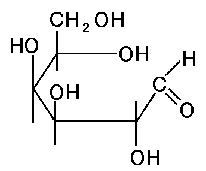
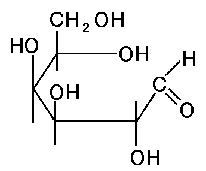
さて、ここでは、アルドヘキソースが環状グルコースになる課程について説明しましょう。
まず、5番炭素の水素が外れ、一番炭素に二重結合している酸素に結合します。でもそのままだと、その酸素の「手」の数が三本になってしまっておかしいですね。ですから、二重結合の内の一方が切れます。
こうなりますと、一番炭素の手の数が「三本」になってしまい、これもおかしいですね。
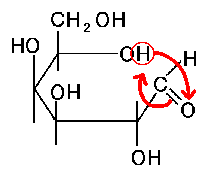
ですから、一番炭素と五番炭素に付いている酸素が結合します。
結果として、環状のグルコースが生じますね。
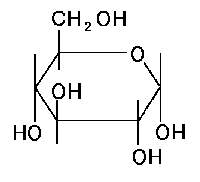
ところで、この一番と五番が結合する場合、一番炭素が回転して、ねじれた形で結合する場合があります。
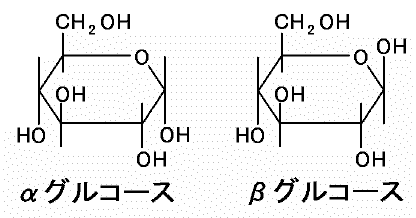
その結果生じるグルコースは、一番炭素に着いた水酸基が、上側にきますね。
どちらもグルコースには違いが無く、性質もほとんど同じなのですが、これが二糖類、多糖類になると、その違いが現れてきますので、区別をする必要があります。
そこで、一番炭素の向きによって、「αグルコース」「βグルコース」という呼び方をします。
要するに、一口に「グルコース」と言っても、「α型」「β型」「アルドヘキソース型」の3タイプがあるんですね。
で、これらは必ず平衡状態として存在します。「α型だけ」とか、「β型だけ」という事はないんですね。
その存在比率は状況によるので一概に言えませんが、
位の比率です。
ここでよ〜く押さえて欲しい事は、「アルドヘキソースは少ないが、0%ではない」事です。「少ない」のと「無い」のは全く違いますからね。この事が、後で影響してきます。
また、このα型、β型というのは、フルクトースやガラクトースにもあります。
引き続き、その話をしましょう。